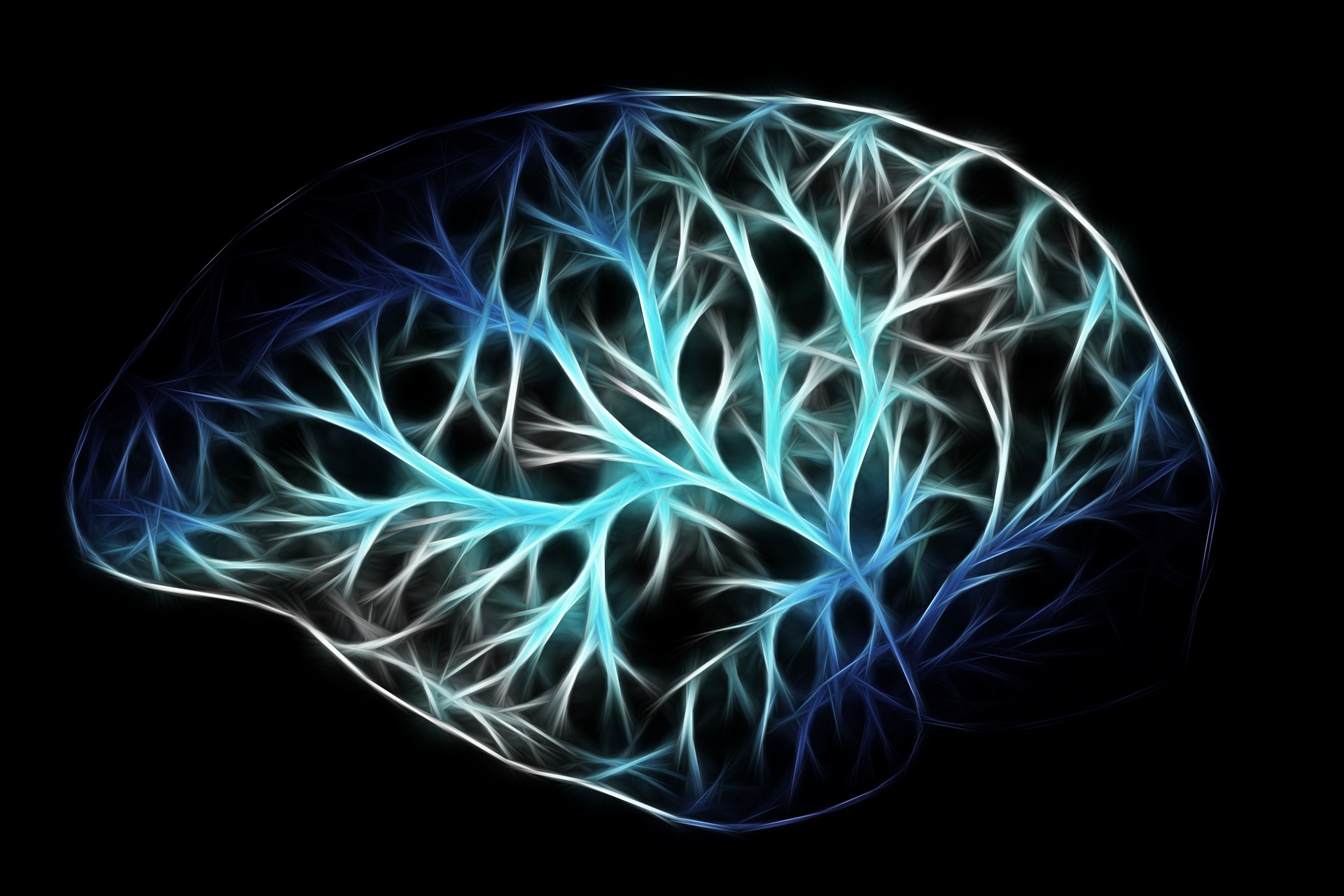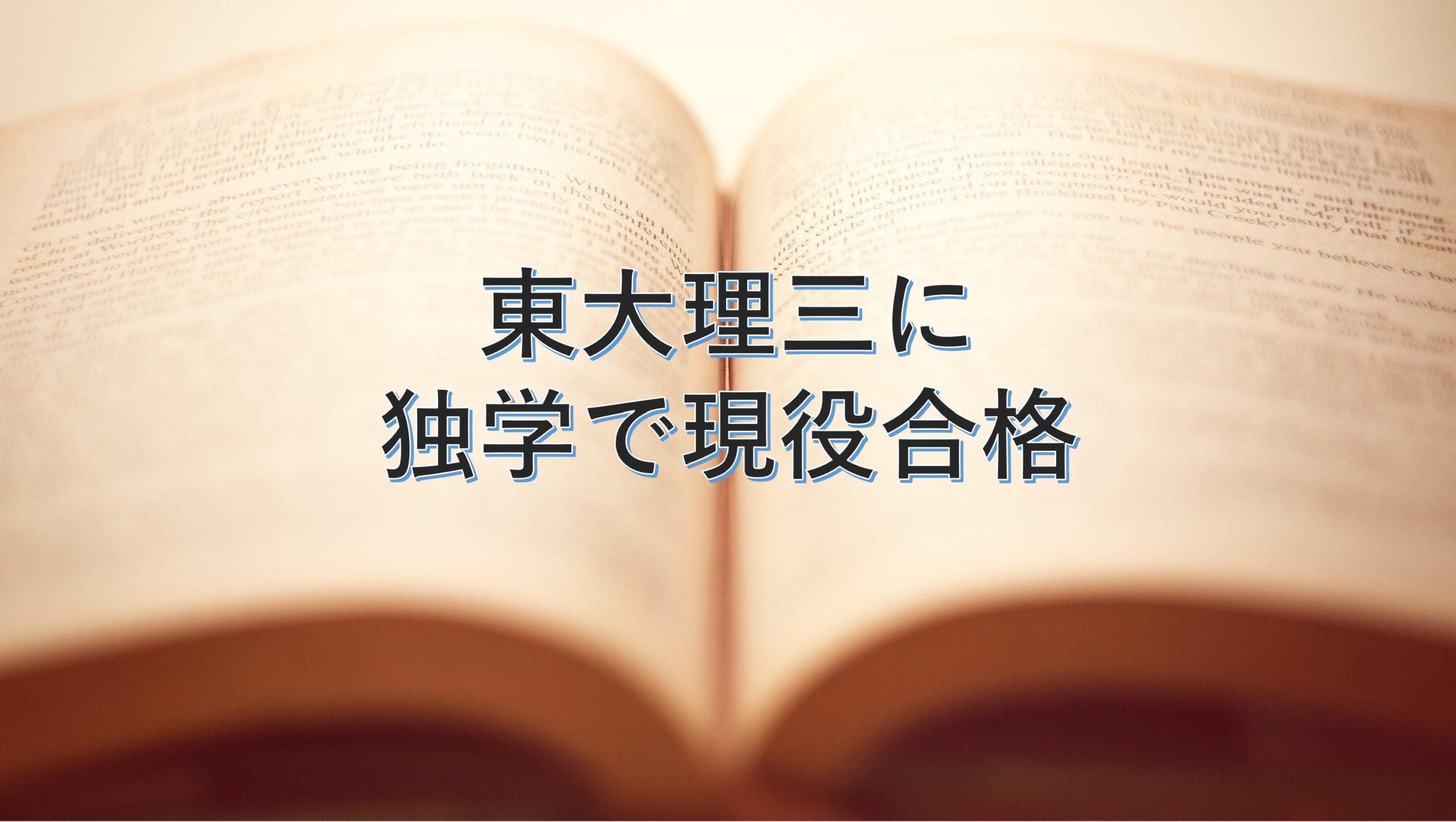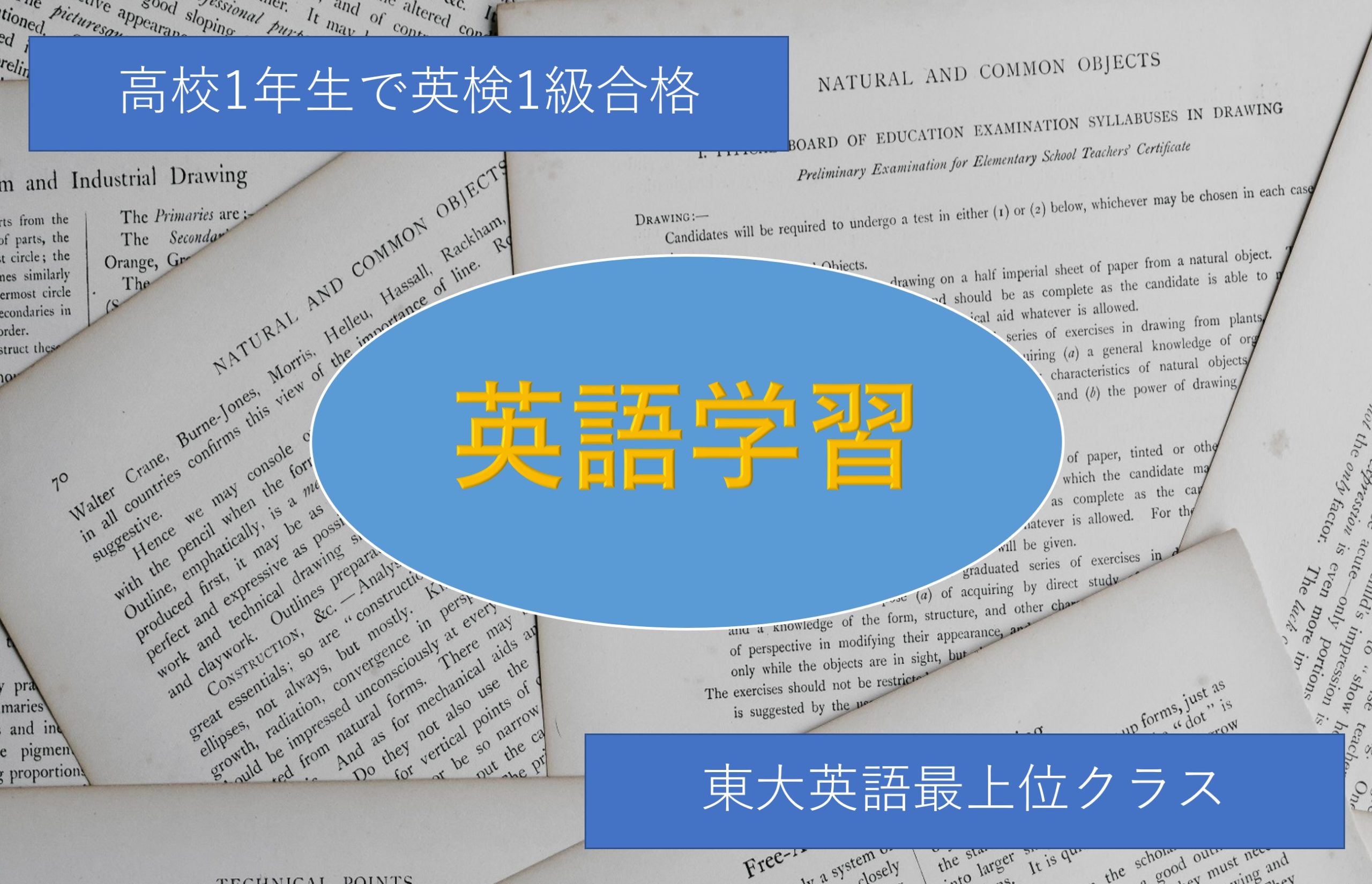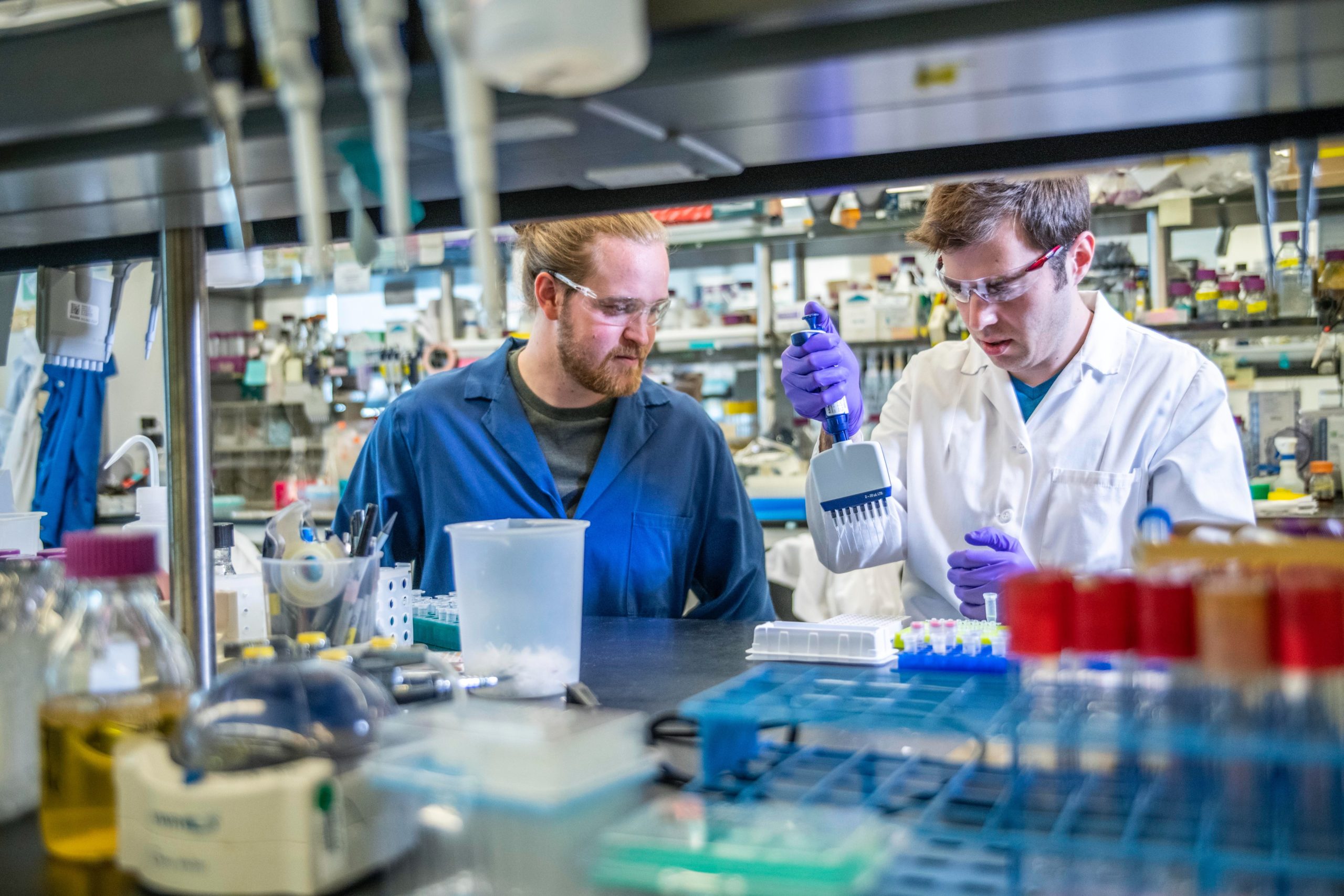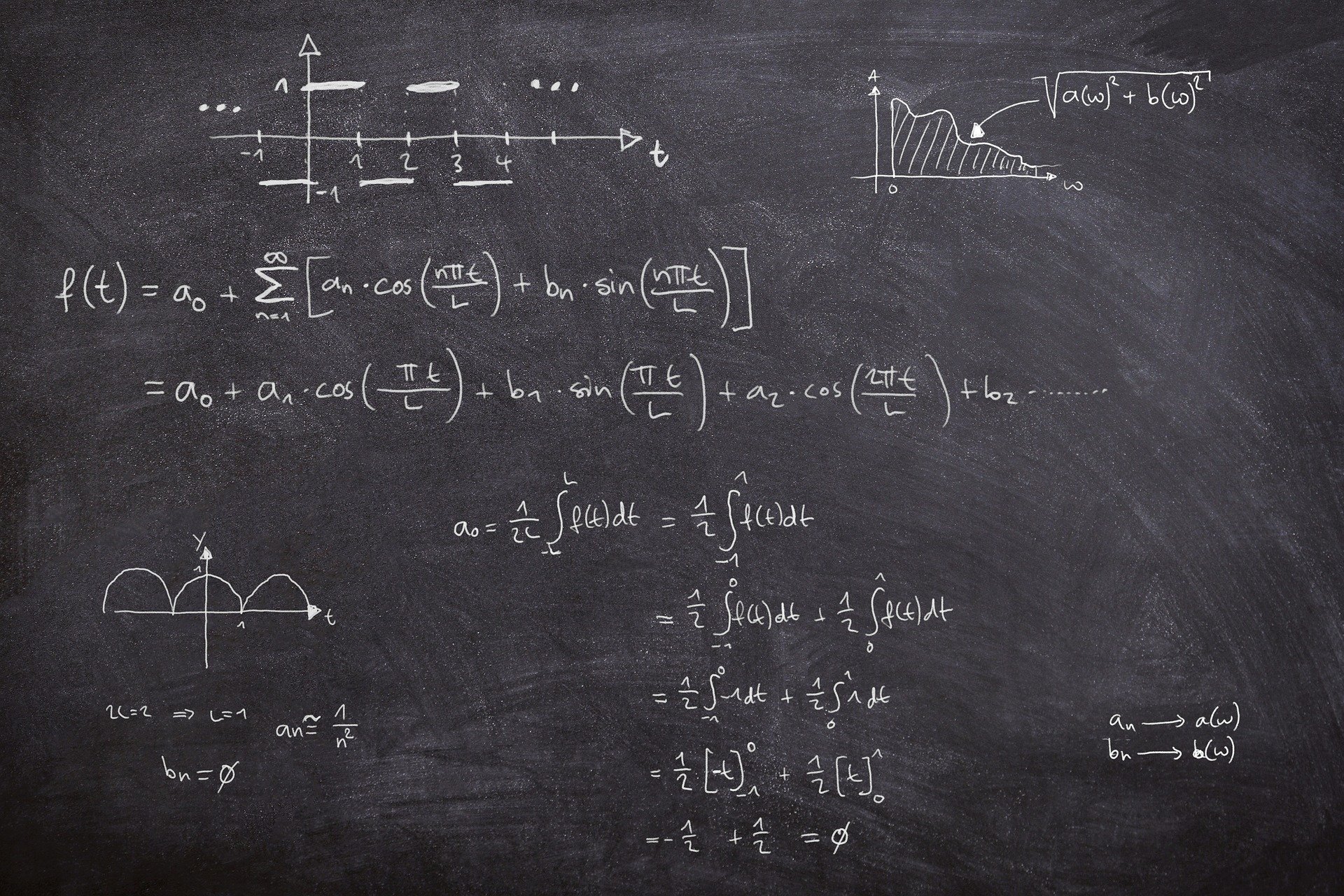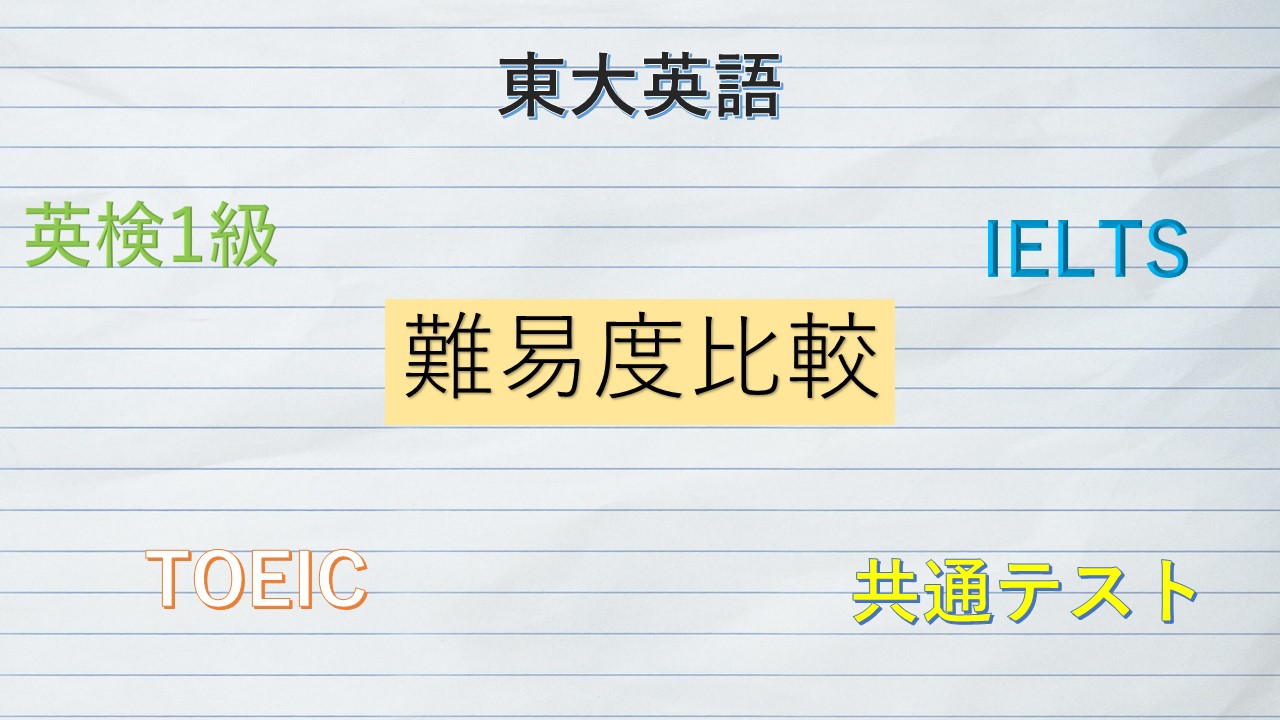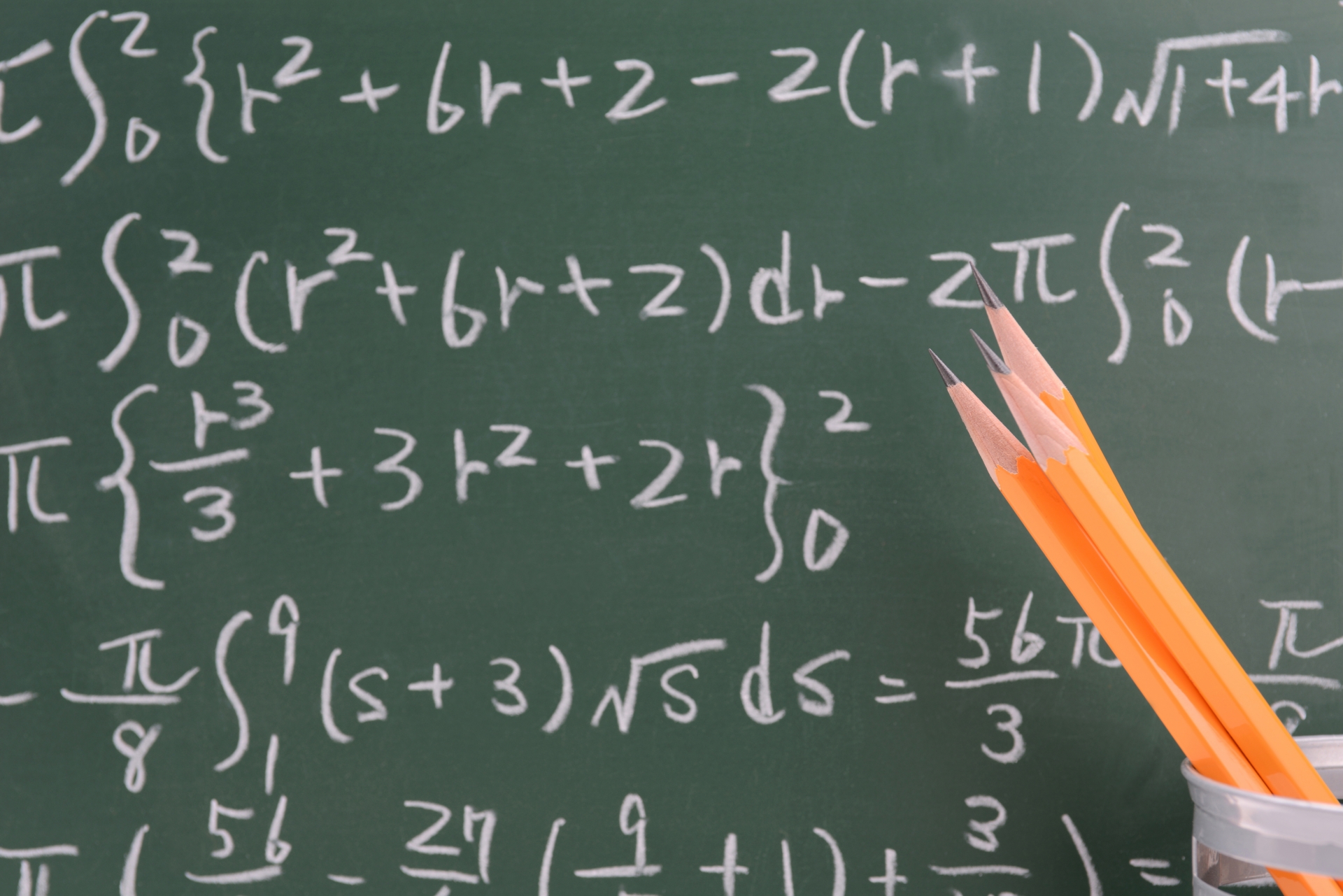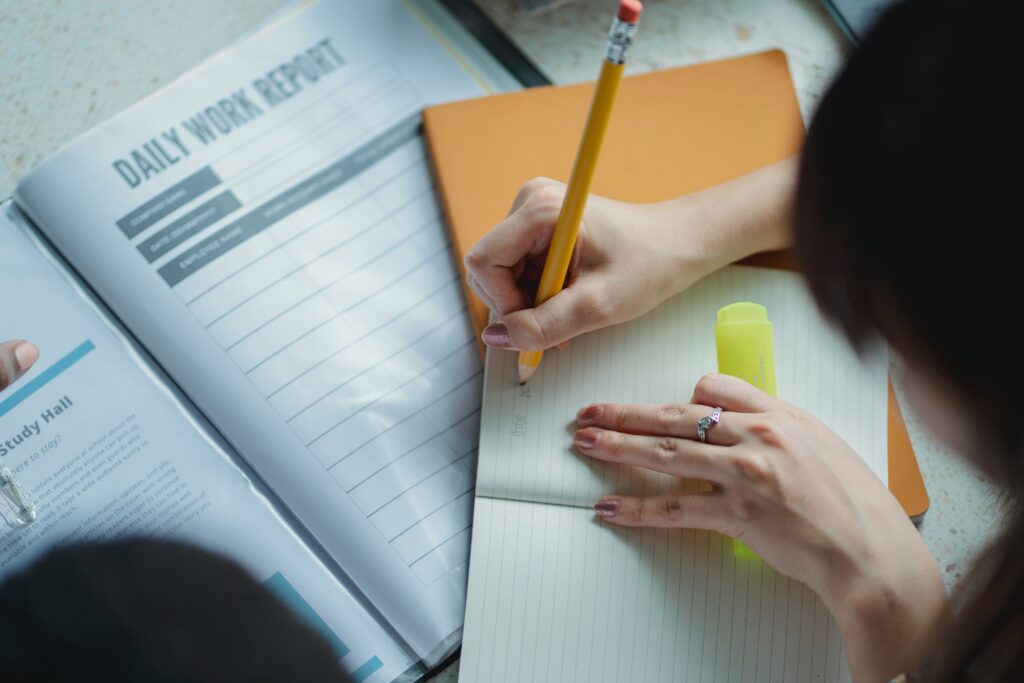
世の中には様々な試験があり、私も色々と試験を受けたことがありますが、どの試験であっても同じような方法で対策を行なっています。
どの試験にも使える基本的勉強法を身につけておき、細かな部分をそれぞれの試験に合わせていくことで幅広い分野の試験に対応できるようになります。
その方法を紹介していきます。
1. 試験についてネットで調べる

試験を受けたいなと考えたとき、最初はその試験についてネットで調べるはずです。これは私もやっていることですし、ほとんどの人が行なうと思うので、どう調べているかについては軽く解説しようと思います。
まずは試験の公式ホームページに行って形式や時期だけは最初に知っておき、そこから実際に受けた人の口コミなどを見て「こんな参考書を使ったのか」などを知っておきます。
ここではなんとなくの雰囲気だけを掴んでおければ良いので、私は普段1~2日くらいでザーッと調べているという感じです。
ここで実際にその試験を受けるのかどうかという決心をします。この時点で「やっぱ受けたくないかも」と感じてしまったら、いったんは勉強を始めないというのも大事なことで、やる気がきちんと続きそうかどうかというのをしっかりと見極めておきましょう。
2. 参考書を使って全体像を掴む
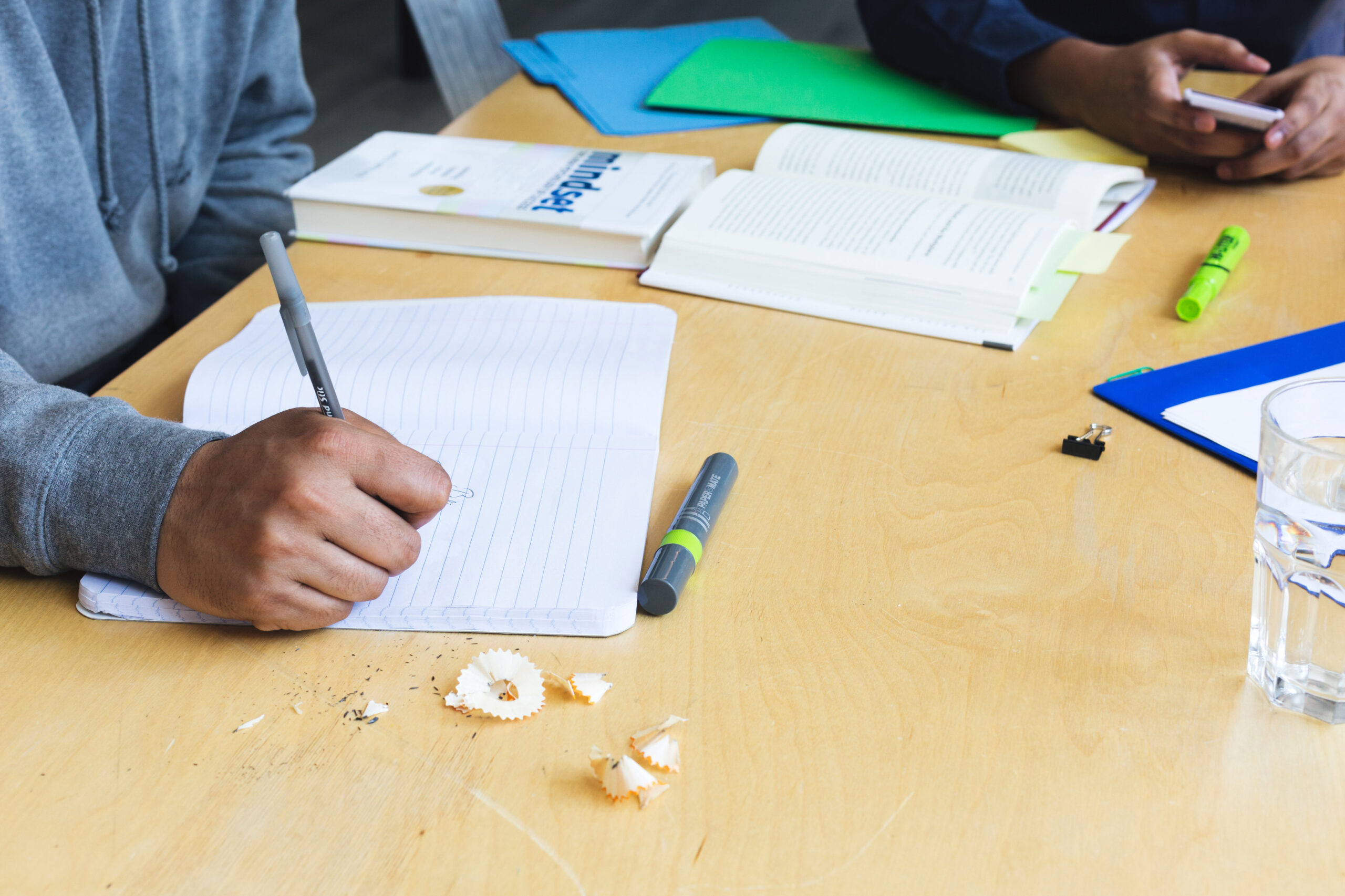
勉強しようと決めてから最初にやることは、1冊標準的な参考書を買ってみて、それをいったん通読することです。
この時点では内容が全然理解できないのは当たり前ですが、そんなのは気にせずに「なんとなくこういうことなのかな」くらいの雰囲気で読み進めていきます。
「全然理解できないのになんでこんなことをやるのか」という疑問はあると思うのですが、明確な理由が2つ挙げられます。
1つ目は、どの部分とどの部分が関連しているのかというのを掴むためです。
参考書は学びやすい順番で書かれているのは当たり前なのですが、それでも後から出てくる知識を持っていた方が学びやすいということがどうしても出てきます。そのため、勉強していくときに前からじっくり進めていくと理解しにくいことが増えてしまうのです。
全体を見通しておいて軽く全体像を掴んでおくとそのような問題がかなり減るはずです。
2つ目は、どのくらいの労力をかけるべきかというのを把握するためです。
勉強を進めるにおいても敵を知ることはとても大事です。全体像を掴んでおけば「目標点を取るためにはこのような方法で勉強をしていってこのくらいの時間がかかるだろう」という大体の目安がわかるはずです。また、どこに特に力を注ぐべきなのかというのも分かってくると思います。
3. 参考書の内容をノートにまとめてから覚えていく

全体を見通すことができたら、初めに戻ってその参考書の内容を頭に入れていきます。
ただ、普通に参考書の内容をすべて頭に入れるのが効率的でないことは分かるかと思います。参考書にはわかりやすくするための解説がたくさん書いてあり、実際に覚えるべき部分というのは結構限られているものです。
そこで、参考書の内容を自分でノートでまとめていくようにします。これは自分専用のノートで、参考書から吸収して暗記するべき内容を自分なりにまとめたものを作っていきましょう。
「参考書の内容をノートにまとめるのって時間かかるし非効率的だ」と感じる人もいると思うのですが、それは大きな間違いだと考えています。
もし参考書を3周読めば覚えられるというような天才であれば別ですが、私を含めて普通の人間であれば何十周もしていかなければ頭に入りきらないはずです。
分厚い参考書を何十周も見返すのではなく、自分なりに必要な部分をまとめて見やすくしたノートを作ってでもそっちを見返していくほうが時間もかからないし確実です。
暗記が苦手という人は非常に多いと思います。かくいう私もあまり得意ではありません。医学部に入ると非常に覚えることが多く、テストのたびに苦労しています。 しかし、受験勉強においては暗記が非常に多くの割合を占めています。最低限 …
4. 問題演習を行なっていく

参考書の内容を頭に入れきったと思ったら問題演習に進んでいきます。
問題演習としては、大きく分けて問題集と過去問があるはずです。それらをどう使いこなしていくかというのが大事になってきます。
最初にやるべきことは、過去問を軽く眺めていき、どのような形式になっていてどのくらいの問題数があってどのくらいの時間制限なのか、というのを掴むことです。これも敵を知るということの1つだと思います。
自分の目標点と照らし合わせて、どのくらいの問題演習が必要そうかなどを考えておきましょう。
次に、問題集で問題演習を積んでいきます。3周は演習をするべきなのですが、それにも方法があります。
1周目は普通に問題を解いて、解答解説を読んで復習していきます。このときに、知らない知識が出てきたらその都度メモをして、後で見直せるようにしておきましょう。
1周目を終えたら、メモした内容を覚えていきましょう。参考書で身につけた基本知識にどんどん後付けしていくというイメージです。
メモを覚えきったら2周目に入っていくのですが、このときは1周目で間違えた問題や知識的に曖昧だと感じた問題をやっていきます。身につけるべき知識を絞って再確認していくという形です。2周目を解いた後の復習で基本的にはすべて覚えていきましょう。
3周目としては、すべての問題を改めて解いていきます。ここでは、スピード感をもって解いていき、全体知識を再確認していくという形です。1周目と同じ問題数を解くわけですが、知識がきちんと入っていればかかる時間は3分の1程度になるはずです。
最後に、過去問を解いていきます。
過去問を解いていく段階では、すでに知識レベルとしては十分なものがあるはずです。そのため、この段階では時間配分を考えてどうやって高得点を取っていくかというのを考えていくべきです。
時間制限が厳しい試験になると特にこの部分が大切になってきます。一般的な資格試験だと、英検1級を受けたときはかなり時間配分に気をつけた覚えがあります。
自分なりに高得点を取るためにどう時間を使っていくかというのを考えておきましょう。
5. 本番当日に向けて準備をきちんと行なう
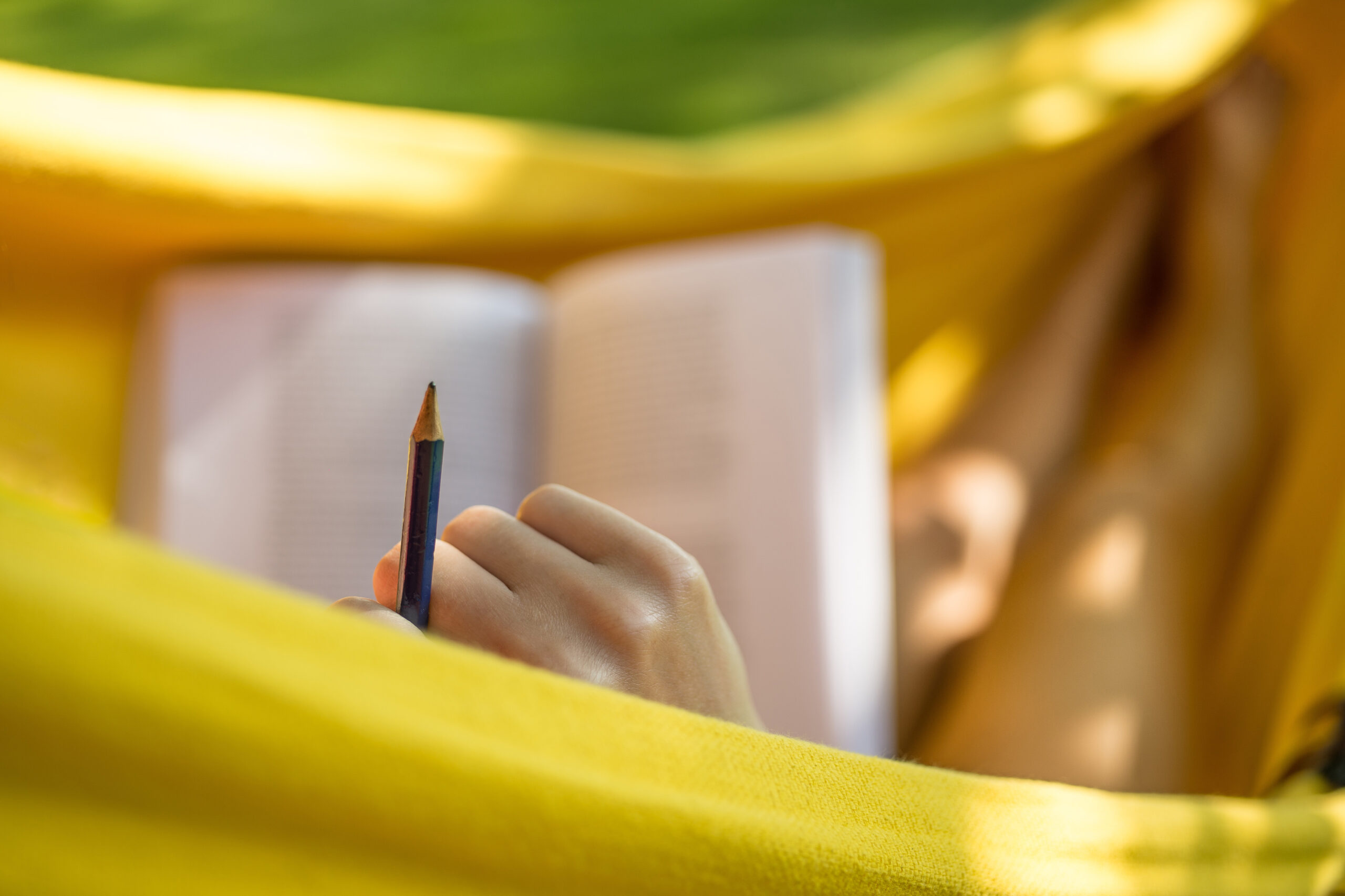
本番前日までに本番の準備をきちんと行なっておきましょう。不安要素がありながら試験を受けるとどうしても集中力が落ちてしまうと思います。
当日何を持っていくか、前日にどう体調を整えておくか、などはあらかじめ考えて準備しておくべきです。「自分はのどが渇きやすいから水を多めに持っていこう」とか「お腹が痛くなりやすいから薬を飲んでいこう」などは本番でのパフォーマンスに大きく集中してきます。
今までの努力を本番で最大限生かしていくためにも直前期にこれらに注意していきましょう。
まとめ
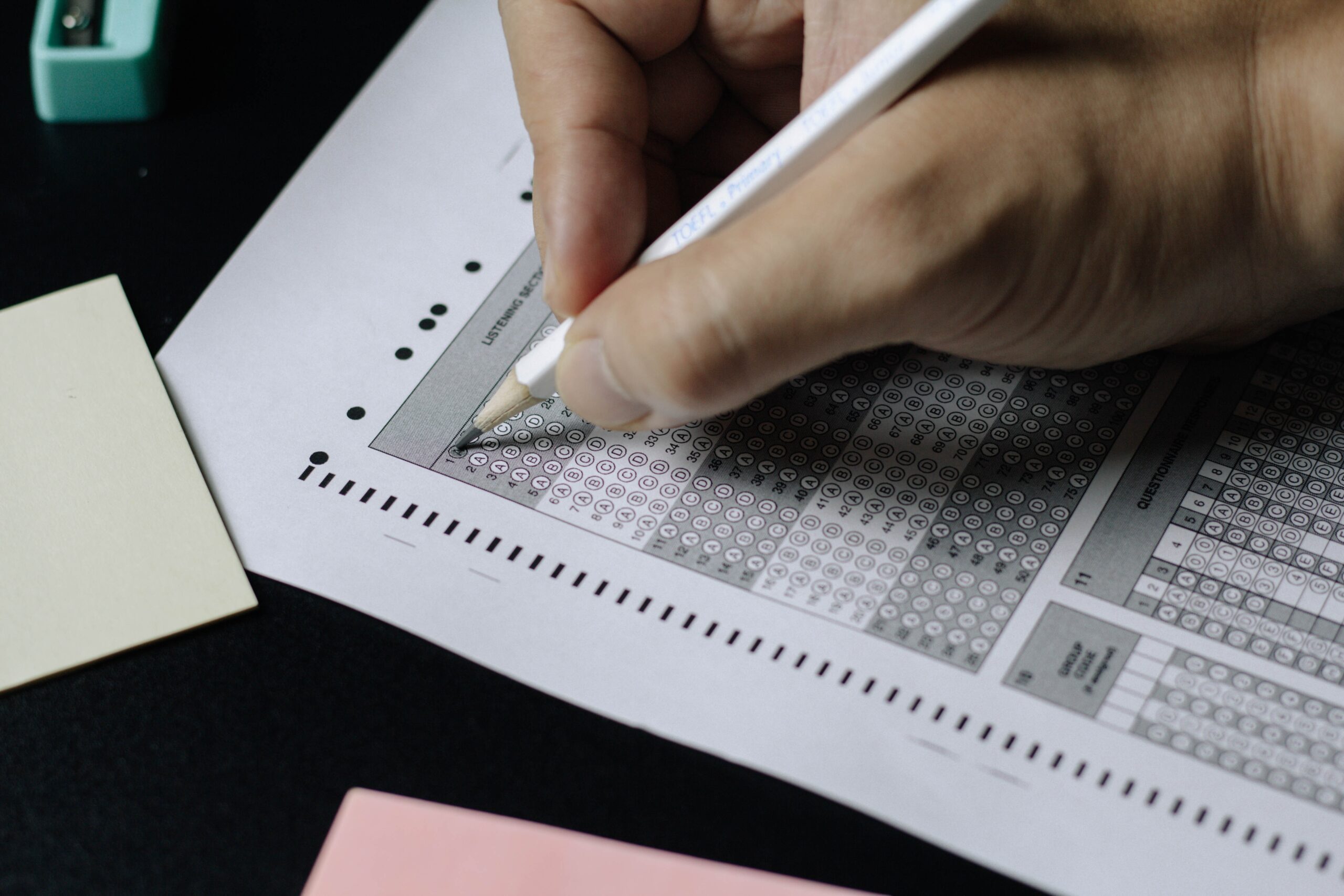
この方法で私は結構色々な試験を通ってきました。実際に取った資格については資格検定のページでも紹介しています。普段、医学の勉強をするときも基本的にはこの流れに沿って行なっています。
幅広く学んでいき、その過程として試験を受けるというのを考えているのであれば、ぜひこの方法を試してみてください。
誰でも独学でできる大学受験対策について、トップレベルの東大生が試行錯誤して成績を伸ばしてきた経験から色々な記事を書いています。 大学受験参考書 受験勉強体験記 勉強法総論 科目別勉強法
英語学習に関連している記事をまとめました。英検1級に高得点で受かる勉強法、IELTSで8.0を取るためにやった勉強法、4技能を継続的に勉強し続ける方法、など色々な記事があります。